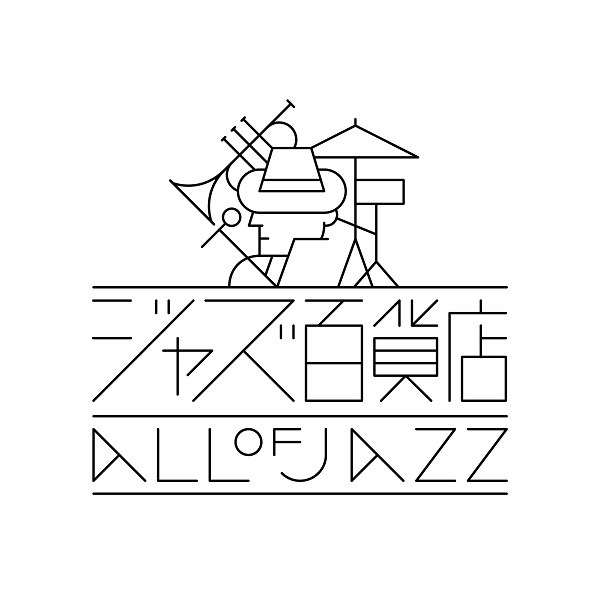Anita O’Day アニタ・オディ リーダー作②黄金のヴァーブ時代
クルーパ、ケントン時代のアニタも素晴らしいですが、バンドシンガーとしてのアニタであり、ソロシンガーとしてのアニタを楽しむのは、やはり52年のヴァーブ以降(1952〜62年の11年間)となります。特にこのページの「ジス・イズ・アニタ」、「シングズ・ザ・モスト」を含む数年間がアニタの絶好調期と言えると思います。(しげどん)
・新宿ジャズ談義の会 :アニタ オディ CDレビュー 目次
・Anita O'Day CDリーダー作① バンドシンガー時代(1941-1959)・・・このページ
・Anita O'Day CDリーダー作② 黄金のヴァーブ期(1955-1962)
・Anita O'Day CDリーダー作③ 麻薬禍からの復活期(1963-1972)
・Anita O'Day CDリーダー作④ 第二の黄金期(1975-1979)
・Anita O'Day CDリーダー作⑤ 晩年を迎えるアニタ(1981-2005)
「アニタ(日本タイトル:ジス・イズ・アニタ)」と「シングズ・ザ・モスト」が2大名盤とされるが、それ以外のヴァーブ盤は、あまり知られていない現状があると思う。そんな中にも聞かれてしかるべき盤があるのではないかという観点から聞き直してみた。その結果、2大名盤に準ずる素晴らしい盤があることが再確認できた。(hand)
(THIS IS) ANITA / Anita O'Day
Anita O'Day(vo),
④⑥⑦⑫:Pal Smith(p), Barney Kessel(g), Joe Mondragon(b), Alvin Stoller(ds)
①②⑧⑩:Pal Smith(p), Barney Kessel(g), Joe Mondragon(b), Alvin Stoller(ds), Milt Bernhart, Lloyd Elliot, Joe Howard, Si Zentner(tb)
③⑤⑨⑪:Pal Smith(p), Barney Kessel(g), Joe Mondragon(b), Alvin Stoller(ds), Corky Hale(harp) + Strings
黄金のヴァーブ時代のアニタの最高傑作
黄金のヴァーブ時代のしかもアニタの最高作とされている盤。この盤も4トロンボーンやストリングも入り一種のビッグバンド盤ではあるが、従前のようなスイング時代のバンドシンガーではなく、アニタとその伴奏をするのがモダンなポール・スミスのピアノを中心に、バーニー・ケッセルのギターも擁したリズム隊+バディ・ブレグマン指揮のジャズオーケストラになっているのが大きな変化だ。「イブニング」から1年足らずだが、録音も格段に進化し、アニタの表現力は微細から大胆まで幅が出て、声のツヤも最高の状態にある。スインギーな曲からバラードまで、名唱ぞろいだ。録音月日が従前は56年2月とされていたが、近年の盤では55年12月6~8日、ロス録音の前年作となっている。「ジス・イズ」は日本で追加されたタイトルで、元は単なる「アニタ」。ヴァーブのレーベルとしての初盤という記念すべき盤。(hand)
アニタ・オディといえば粋なカッコよさ。それが最大限に発揮された傑作盤。冒頭のYou're The Top!で後半歌詞を変えてYou're The Bop!と、サラ・ヴォーンやチャーリー・パーカー,マイルスまで登場させるあたりは、ジャズヴォーカルらしい粋なかっこ良さだ。伴奏はバディ・ブレグマン楽団ということだが、すべてがフルオーケストラではなく、ポール・スミス(p)、バーニー・ケッセル(gr)を擁するカルテット、それに4トロンボーンを加えたもの、そしてストリングスを加えたフルオーケストラと、曲調により編曲も工夫された変化に富んだ一枚。ポール・スミスのセンス良いバッキングが光り、特にカルテットによるWho Cares?でピアノがアニタのボーカルに絡むあたりのジャズ的な魅力などは素晴らしい。(しげどん)
素晴らしい!アニタのイキイキとした歌いっぷりは、色褪せることなく今でも聞き惚れてしまう。軽やかなノリとハスキーな声色は他の誰に変えることのできない彼女の武器で、このアルバムではそんなアニタの魅力を隅から隅まで感じることのできる名盤だろう。 (ショーン)
PICK YOURSELF UP / Anita O'Day
Anita O'Day(vo),
①②⑤⑩:Harry Edison(tp), Larry Bunker(vib), Paul Smith(p), Barney Kessel(g), Joe Mondragon(b), Alvin Stoller(ds)
③④⑥‐⑨⑪⑫:Buddy Bregman and His Orchestra
Conte Candoli(tp), Milt Bernhart, Frank Rosolino(tb), Harb Geller, Bud Shank(as), Georgie Auld, Bob Cooper(ts), Jimmy Giuffre(bs), Paul Smith(p), Al Hendrickson(g), Joe Mondragon(b), Alvin Stoller(ds) + Strings
「ジス・イズ」と「モスト」という二大名盤に挟まれた盤
近年、「ジス・イズ」の録音月日が56年2月から55年12月に修正され、「シングズ・ザ・モスト」も56年5月から57年1月に修正されたことで、「ジス・イズ」と「モスト」という両大名盤の間に挟まれることとなった盤(56年盤はこの盤だけとなった。)。それまではコンボでの最高作「モスト」の次のセカンドベストの盤のような印象だったが、オーケストラ入りの「ジス・イズ」から「モスト」に至る経過の盤として聞くと編成的にもハリー・エディソン・セクステットとバディ・ブレグマン・オーケストラの2組がバックというのが理解しやすくなった。両名盤に比べて劣るものがあるとすれば選曲ではないかと思う。両盤は印象的な名曲ばかりなのに、この盤は記憶に残る美メロの曲が少ない。唯一いい曲と思うのは、②レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンスだけだ。①その手はないよ、④サボイなどはスイング時代の曲で古臭ささがこの時点では漂い始めている。
※輸入盤では9曲追加の拡大盤もある。同一セッションからは3曲(⑳アイビーのみ初。2曲は別テイク)だけで、それ以外は56年1月の2曲、2月の4曲があり、内容はともかく(笑)、この盤のみで聞かれる貴重な演奏ではある。(hand)
ANITA SINGS THE MOST / Anita O'Day
Anita O'Day(vo), Oscar Peterson(p), Herb Ellis(g), Ray Brown(b), John Poole(ds)
モダン・ジャズ・ボーカルのお手本とも言える大名盤
「ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン」とともに、ジャズを聞き始めた当初から聞いている愛聴盤。古いLPやCDでは録音が56年5月10日となっていたが、近年のCDでは57年1月31日となっていて、56年12月の「ピック・ユアセルフ・アップ」の前から後ろとなった。ハーブ・エリスのギターとレイ・ブラウンのベース入りのオスカー・ピーターソン4というヴァーブ最強かつシンプルなリズム隊とバンドシンガー的な唱法から脱した絶頂期のアニタの組合せ、そしてアニタ向きの名曲11曲がうまく選曲・配置され、どの曲も、歌謡曲のヒットシングル盤のように耳に残る。モダンジャズボーカルのお手本とも言える大名盤だと思う。(hand)
オスカー・ピータソン・カルテットという最重量級のバックを得て、聞きなれたスタンダードをジャズらしく唄うアニタ。有名スタンダードでもテンポなどを工夫し、アニタらしいオリジナリティあふれる味付けがされていて、冒頭のS’WondefulなどもThey Cant Take Awayが間に挟まり変化に富んでいる。ピーターソンの凄腕テクニックは安定感抜群だ。(しげどん)
まとまりのない雑多な印象のアルバム。録音があまり良くないのせいなのか、アニタの声はがさついて重苦しく感じる。重い低音ばかりが耳についてしまい、厳しめに言うと、あまり長く聴いていられない。ジャケットの写真も微妙。(ショーン)
ANITA O'DAY SINGS THE WINNERS
Anita O'Day(vo)
⑦-⑫:with Russ Garcia and His Orchestra
①-⑥:with Marty Paich and His Orchestra
ジャズ史に残る有名曲をアニタが歌うという企画盤
スイングからモダンまでのジャズヒット曲をアニタが歌うという企画盤。ディジーやマイルス、マリガンなどのモダンな選曲もあるが、多くはエリントン、グッドマン、ハーマンなどスイング系だ。ビッグバンド演奏でもあり、全体の雰囲気はスイングになっているのが時代的に惜しいところ。前半6曲がマーティ・ペイチ、後半6曲がラス・ガルシアとモダンなアレンジャーではあるのだが、やはりモダン感は弱い。同じペイチがアレンジした1年後のアート・ペッパーの「プラス11」ではかなりモダンな選曲となっているのでやはり少し早かったのだろう。オマケに入った7曲はヴァーブの他盤からの音源で、別テイクは元盤に収録すべきと思うが、今回はヒット曲集に単に有名曲を追加したノリと想像する。(hand)
ジャズ史に残る有名曲をアニタがボーカライズ。A列車やチェニジアの夜のような超有名曲はスタンダード化されている。でもアーリー・オータムやフォア・ブラザーズなどはスタン・ゲッツやズート・シムズを語るうえで外せない歴史作だが、カバー作品は比較的珍しいのではないかと思うので楽しく聴けた。ジミー・ランスフォードの「ホワッツ・ユア・ストーリー・・・」なども、スィングファンにはうれしくなる渋い選曲だ。(しげどん)
スタンダードばかりの軽快なアルバム。幅広く歌いこなすアニタの魅力満載だ。全て短い曲ばかりなので、一気に聴き終わってしまい、もう少しじっくりアニタを聴き込みたい向きには少し物足りなく感じるだろう。(ショーン)
ANITA O'DAY AT MISTER KELLY'S
Anita O'Day(vo), Joe Masters(p), Larry Woods(b), John Poole(ds)
「ウィナーズ」の3週間後のシカゴでのクラブライブ
「ウィナーズ」をロスで録音した3週間後の故郷シカゴでのクラブ(レストランらしい)でのライブ。終生共演するドラムのジョン・プール以外は、知らないピアノとベース。プールはロード・マネージャーもやっていたようだ。有名な映画「真夏の夜のジャズ」が1958年7月3日〜6日のニューポート・フェスなので、その3か月前になる。「真夏」は、2021年、リマスター盤DVDが発売されたり、映画が再上映されるほどの名作であり、アニタの出演は映画では2曲だが、歌唱、衣装も含めて映画のハイライトの一つになっている。それに対しこの盤は、レストランでのくつろいだ演奏なので、多少緊張感と盛り上がりに欠ける気がする。(hand)
ANITA O'DAY SWINGS COLE PORTER WITH BILLY MAY
Anita O'Day(vo) with Billy May and His Orchestra
ビリー・メイのビッグバンドとのコール・ポーター集
ビリー・メイ楽団という多少スイートなビッグバンドとの共演によるコール・ポーター作品集。私はコンボ作品が好みだが、バンドシンガー出身のアニタはこの手のスタイルが好みのようでイキイキしているように感じられる。大向こうを唸らせるようなスタイルが気に入っているのだろう。私の所有する輸入盤には別テイクの6曲が入っていて、ヴァーブ他盤からのポーター曲を親切に集めたようだが、あまりありがたくない印象を持った。特に追加曲の1曲目⑬ユア・ザ・トップは、名盤「ジス・イズ」の冒頭曲なので、盤が変わった感が強過ぎる。オマケのない盤、翌60年の同じビリー・メイとの「ロジャース&ハート」とカプリング盤もある。(hand)
ビリー・メイの編曲と指揮によるビッグバンドをバックにしたコール・ポーター作品集。有名曲がずらりと並ぶが、ビリー・メイの編曲は割と複雑なアレンジでリズムにも変化を持たせているが、実験的な堅苦しさはなく、リラックスして聴ける上に飽きさせないプロの仕事だ。ビッグバンドシンガーであったアニタのカッコいい粋な魅力を引き出すのに成功している。(しげどん)
COOL HEAT / Anita O'Day Sings Jimmy Giuffre Arrangements
Anita O'Day(vo) with Jimmy Giuffre and His Orchestra
ジミー・ジュフリーのスモール・ビッグバンドとの共演盤
ジミー・ジュフリーのアレンジと指揮によるスモール・ビッグバンドとの共演盤。データでは、「コール・ポーター」の2回の録音の合間に録音されている。マラソン・セッション並みにすごいことだ。アニタの脂が乗っている時期だったのだろう。西海岸オールスターのようなメンバーで、アート・ペッパーが4曲に入っているのだが、ソロはないのが非常に残念。全体にややアレンジ過多で、いいと思えたのはスインギーな⑨ハーシー・バー、⑫今宵の君くらいだった。(hand)
SWING RODGERS & HART / Anita O'Day & Billy May
Anita O'Day(vo) with Billy May and His Orchestra
ポーター集の続編的なロジャース&ハート集
今回はストリングスも多用したビリー・メイのかなりスイートなビッグバンドとの再共演。「コール・ポーター」、「クール・ヒート」というこの時期の似た盤3枚の中では、この盤が出来がいいと感じた。アニタの気に入った編成と、ロジャース&ハートの曲が合っているのか、とてもイキイキした歌声になっている。「ジス・イズ」に近い好調さも感じる。(hand)
ビリー・メイとのコール・ポーター集の続編的なロジャース&ハート集。ストリングスも使っている一般受け寄りのアレンジで、曲調のせいもあろうが、前作の歯切れの良いジャズらしいカッコ良さに比べてややしっとりとした歌唱が多い印象。アニタのボーカルはつややかだ。(しげどん)
アニタの可愛らしい歌声が満喫できる楽しいアルバム。バックにビッグバンドを従えたアニタの歌いっぷりはレトロな雰囲気の中、小気味良くリズムに乗って、心がぽっと明るくなる。(ショーン)
WAITER MAKE MINE BLUES / Anita O'Day
Anita O'Day(vo) with Russell Garcia and His Orchestra
ブルースを歌うアニタ。バド・シャンクのアルトとフルートもいい。
いい盤は、いいベースが聞こえる盤であることが多い。この盤は、ブルースを歌うアニタ、そしてラッセル・ガルシアの控えめなアレンジと、バド・シャンクのアルトとフルートのソロで知られている盤だ。聞いてみると、アル・マッキボンのベースがまさに盤のベースをいい感じで支えているのを感じた。トロンボーンアンサンブルを多用したオーケストレーションもいい。「ジス・イズ」でも使っていた手法だ。ただ、ストリングスとハープが入った曲は甘口になっている②エンジェル・アイズのようなアレンジは私的には減点要素だ。私はジャズハープは決して嫌いではなく、ソロ楽器としてはむしろ好んで聞いている。しかし、ストリングスと合わせて甘口度を上げるような使い方は苦手としか言いようがない。12曲中3曲②⑦⑪と少ないのが救いだ。ジャケは最高にカッコいい。(hand)
アニタのつややかなボーカルの魅力に焦点が当たった一枚。この時期のアニタのボーカルは実に魅力的だ。バックを勤めるラッセル・ガルシアも編成に変化を持たせたアレンジで工夫している。バド・シャンクのフルート、アルトもそれなりに聴きどころなのだろうが、全体的にはポピュラー寄りのアレンジと感じ、ビリー・メイとのコンビでやったロジャース&ハート集に近い雰囲気がある。裏面のジャケ解説にはハワード・ロバーツの名前もあるが、正しいパーソナルはどうもハッキリしない。ヴァーブはこのあたりは実にいい加減なので、詳しい方は教えてほしい。(しげどん)
バックバンドのフルートやアルトがバラエティに富んだ世界の広さを感じさせ、アニタの声がとても伸びやかにまた自由に感じられる。ドラマチックな映画のような景色感を感じることのできる素敵なアルバムだ。(ショーン)
INCOMPAREBLE! / Anita O'Day
Anita O'Day(vo) with Bill Holman and His Orchestra
Charlie Kennedy, Joe Maini(as), Richie Kamuca, Bill Perkins(ts), Jack Nimitz (bs), Conte Candoli, Al Porcini, Ray Triscari, Stu Williamson(tp), Bob Edmonson, Lew McCreary, Frank Rosolino, Kenny Shroyer(tb), Lou Levy(p), Al Hendrickson(g), Joe Monddragon(b), Mel Lewis (ds)
ビル・ホルマンのビッグバンドとビリー・ホリディ集
1961年に「アイ・リメンバー・ビリー・ホリデイ」として発売される予定が中止になり、64年に現在の「インコンパラブル」のタイトルで発売された盤。なので、次作「トラヴェリン・ライト」とビリー集という意味ではコンセプトは同じ。アレンジと指揮は、ビル・ホルマン。「トラヴェリン」が録音した61年にすぐに発売されているのに対し、こちらはアニタがヴァーブを離れてから発売なので、多分、没盤なのだろう。では、実際に聞いてみてどうかといえば、アニタの歌は好調期なので特に違いは感じない。バンドの演奏はかなり違う印象で、こちらのほうが本格的なビッグバンド演奏で、ベイシー楽団的なダイナミクスのある演奏だ。想像ではあるが、スイートバンド的な、日本で言えば歌謡曲のような演奏の方が売れるので、この盤はお蔵入りしたのではないか。ただ、ビリー集にしては、威勢が良くカラッとしていて、暗いビリーの歌唱とは対極にあるような盤だと思う。(hand)
TRAV'LIN' LIGHT / Anita O'Day
Anita O'Day(vo),
①③⑨-⑫:Russell Garcia Sextet
②④-⑧:Johnny Mandel and His Orchestra
ラス・ガルシア6とジョニー・マンデルのビッグバンドとビリー・ホリディ集
シングズ・ビリー・ホリデイ的な盤。聞いていてアニタとビリーとの共通点はあまり感じないが、やはりアニタも、大御所ビリーはリスペクトしていたらしく、フレージングは学んでいたようだ。ただ、威勢よくスインギーに歌うアニタにビリー的な曲は合うものと合わないものがあると思う。⑥月光のいたずら、などスインギーに歌える曲は、ビリー曲にアニタらしい別の個性をもたらしている。アレンジの半分は「ウエイター」に続くラッセル・ガルシアが19日、残り半分はジョニー・マンデルが18日で、曲は混ぜこぜに入っており、指揮はマンデル、プロデュースはガルシアと、仲良く役割分担しているようだ。(hand)
ALL THE SAD YOUNG MEN / Anita O'Day
Anita O'Day(vo) with Gary McFarland and His Orchestra
Walter Levinsky, Phil Woods(as,cl), Jerome Richardson, Zoot Sims(ts), Bernie Glow, Doc Severinsen, Herb Pomeroy(tp), Billy Byers, Willie Dennis(tb), Bob Brookmeyer(valve tb), Hank Jones(p), Barry Galbraith(g), George Duvivier(b), Mel Lewis(ds)
ゲイリー・マクファーランドのモダンなビッグバンドと歌うアニタ
初の?ニューヨーク録音は、ゲイリー・マクファーランドのアレンジで、モダンなビッグバンドが演奏。アニタは基本的にはスイング時代のバンドシンガーを引きずっていたので、強烈にモダンな感じは初めてだと思う。ベイシー等のスインギーな感じではなく、クラーク=ボラン以下、サド=メル以上という感じでかなりモダンなこのバンド。アニタは一応無事にこなしてはいるものの、微妙に噛み合っていないように感じる。フィル・ウッズのアルトソロ(一部クラ)が光っている。アニタらしくはないが、カッコいいジャケで、インパルスの63年のフリーダ・ペイン盤と少し似ていると思う。アニタのほうが2年古い。(hand)
TIME FOR 2 / Anita O'Day With Carl Tjader
Anita O'Day(vo), Cal Tjader (vb,ds), Bob Corwin, Lonnie Hewitt(p), Freddy Schreiber(b), Johnny Rae(ds,vb)
ラテン系のカル・ジェイダー4との共演
久々のコンボ作は、ラテン系のカル・ジェイダー4との共演。ラテン曲と4ビート曲が交互に入る構成で飽きさせない。アニタは、後年、ボサも得意とするようになるが、この時期は初挑戦の時期で、既に適合ぶりを示している。クリード・テイラーのプロデュースだが、この時期はまだCTI的なあざとい盤にはなっていない。(hand)
カル・ジェイダーとの双頭盤で、ジェイダーのヴァイブを多くフィチュアーし、かつラテン的なアレンジがこの盤の特徴で、聴きなれたスタンダードでもラテン調のアレンジで珍しい。さすがにアニタはそのような変則的なアレンジでもしっかりかっこよくスィングしている柔軟さだ。後半はあまり知らない曲が多いがしっとりと歌うアニタはいい感じだ。全部がラテン的なアレンジではなく、ジャズらしい曲もあり変化に富んでいるとも言えるが、一曲が短く多くの要素を詰め込み過ぎの感もある。ラテンテイストに徹底してもっと一曲を長くとったほうが好印象だったかもと思う。(しげどん)
アニタの魅力的なヴォーカルが素晴らしい。Johnny Raeのヴィブラフォンの華やかな音色と柔く響くFreddy Schreiberのベースに後押しされて、しなやかに軽やかに舞うように歌っている。(ショーン)
ANITA O'DAY & THE THREE SOUNDS
Anita O'Day(vo①③⑤⑦⑨⑩⑪), Gene Harris(p), Andrew Simpkins(b), Bill Dowdy(ds), Roy Eldridge(tp⑦⑪)
ヴァーブのラスト作はスリー・サウンズとの共演盤
ヴァーブのラスト作で、62年に録音・発売されている(ただし、60年録音の「インコンパラブル」が64年に発売)。アニタの登場が約半分のこの盤、そのせいか、いつ聞いても中途半端な感じが漂ってしまう。アニタもスリー・サウンズも決して悪い出来とは思えない。それぞれで1枚分録音して発売してくれたら、どちらもなかなかの盤になったと思える内容だ。アニタに限って言えば、⑦ウィスパー・ノットや⑩貴方と夜、のような、モダンジャズのヒット曲を中心にして欲しかった。この2曲は最高の出来だと思う。この2曲のような路線で行けば、モダンボーカリストとしてのアニタの新たな道を切り開けた気もする。ちなみに3サウンズでは⑧ブルース・バイ・ファイブが素晴らしく、両者ともに旧B面5曲がいい内容だ。旧A面5曲はアニタ入りの3曲が全てバラードで、アニタのスインギーな本領が発揮できていない。日本盤追加4曲のうちロイ・エルドリッジとの⑪レット・ミー・オフの再演は雰囲気が合わず絶対に入れないで欲しかったので、とりあえず没テイクにしたのは正解ではあるとは思うが…それでも私の苦手なプロデューサー、クリード・テイラーの盤作りは理解に苦しむ。(hand)
演奏は素晴らしいがアルバムの編集としてはどうか?という名盤がジャズ史には多く存在するが、この一枚もそのようなアルバムだ。アニタは、オーケストラを従えた盤が多かったので、ピーターソンがバックを勤めたSwings The Mostのような名盤を期待する。でも、アルバムとしてはかなり雰囲気が違うのだ。スリーサウンズのバッキングはすばらしく、アニタ・オディの新たな魅力を引き出している。でも10曲中4曲はスリーサウンズのインストナンバーなので、スリー・サウンズに耳が行ってしまう。というのはこの4曲がかなりいい感じなのだ。アルバムとしての統一感はどうかと思うが、スリーサウンズは、バッキングもトリオ演奏も良いので、この寄せ集め感もヴァーブらしく、ジャズらしい名盤だ。ロイ・エルドリッジが一部客演していて、CD追加テイクでは往年の「Let Me Off Uptown」もやっている。なぜこの企画でこの曲を、しかも当時のルーティンでさせるのか?理解に苦しむがどうせ没にするなら、最初からさせずに普通のスタンダードをさせたら良かったのにと思うが、エルドリッジがそうしたかったのか?(しげどん)
しっとりと歌い上げるアニタ。このアルバムでは、アニタが歌っていない曲が半分あるが、Gene Harrisのピアノ、Roy Eldridgeのトランペットが奮闘していて、jazzのアルバムとしてのまとまりは良い。でもやっぱりアニタが歌った方が圧倒的に曲は引き締まる。(ショーン)
・新宿ジャズ談義の会 :アニタ オディ CDレビュー 目次
・Anita O'Day CDリーダー作① バンドシンガー時代(1941-1959)・・・このページ
・Anita O'Day CDリーダー作② 黄金のヴァーブ期(1955-1962)
・Anita O'Day CDリーダー作③ 麻薬禍からの復活期(1963-1972)
・Anita O'Day CDリーダー作④ 第二の黄金期(1975-1979)
・Anita O'Day CDリーダー作⑤ 晩年を迎えるアニタ(1981-2005)